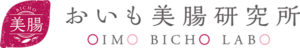最新の記事
知ると納得!意外と深いさつまいもの歴史を解説
さつまいもの歴史ってみなさんご存知でしたでしょうか?
今はスーパーで当たり前に並んでいるさつまいもですが、実はさつまいもが誕生した国は日本ではないんです!
後に日本全土に広まることとなったのですが、さつまいもは地域によって、その呼び名が異なるのです。
当たり前に各地方で使われているさつまいもの呼び名と、どうしてその呼び名になったかを、さつまいもの歴史から紐解いていきましょう。
1.さつまいもの歴史
1-1.さつまいもは元々日本の食べ物ではない
さつまいもの生まれはメキシコを中心とする熱帯アメリカです。
紀元前800~1000年ほど前に誕生しました。紀元前200~600年前のさつまいもをかたどった土器も見つかっています。
その後、15世紀にコロンブスがヨーロッパへ持ち帰ったことでヨーロッパで広まり、東南アジア→中国→日本という流れで日本にさつまいもがやってきました。(諸説あり)
1-2.最初に日本に上陸したところ
1600年ごろ中国から琉球(今の沖縄県)に入ってきました。
奄美大島には、1630年台にはさつまいもが伝えられていたといわれています。
1698年に種子島の島主である種子島久基が、今の沖縄(当時の琉球王国)のさつまいも(甘藷「かんしょ/当時の名称」)のうわさを聞いて、送ってもらったことで、薩摩(今の鹿児島県)に広がり、八代将軍の徳川吉宗の時代に蘭学者の青木昆陽によって全国に広がったと言われております。
その当時は埼玉県川越市がさつまいもの産地で、江戸からは十三里、離れていたので、その当時の焼き芋屋のことを「十三里」と呼んでいたそうです。
それになぞらえて、焼き芋屋が「栗(九里)より(四里)うまい十三里(9+4=13)」とふれて販売していたそうです。
1-3.さつまいもの名前の由来
さつまいもの名前の由来は、琉球(今の沖縄)から薩摩(今の鹿児島県)に伝わったことから「さつまいも」と呼ばれるようになりました。
国内の一部地域では中国から来たという意味の「からいも」や、中国と同じ名称の呼び名の「かんしょ」と呼ぶ地域が今でも残っています。
1-4.さつまいもが日本で栄えた理由
1732年の享保の大飢餓が起こった時に、その当時の総軍徳川吉宗が九州で飢餓の発生率が少ないことに目を付け、さつまいもの生産の推奨を始めたのが日本全土に広まったきっかけです。
日本全土に広める際の助役者となったのが、江戸の町奉行から紹介された蘭学者の青木昆陽です。
青木昆陽にさつまいもにかかわる翻訳書を作成させたことによりその生産方法が確立され日本全国にさつまいもが広がりました。
(出典元:Wikipedia)
まとめ
今や、当たり前にスーパーでよく見かけるさつまいもですが、実は船に乗って長旅の中やっと日本にたどり着いて広まったのですね。
その長旅の中でもいろんな品種が生まれました。
国内に入ってきてからも品種改良が進められ、用途に合ったさつまいもの開発が今でも行われています。
さつまいものゆかりの土地を巡ってみると面白いさつまいもの食べ方に出会えるかもしれませんね。
さつまいもの色々な呼び方とその由来について
これからさつまいもの季節になってきました。栄養がたっぷりで、今や女性が大好きなこの食材がどうして「さつまいも」とよばれるようになったのかご存知でしょうか?
日本にくるきっかけになったことも踏まえ見ていき、知識を深めていきましょう!
1.さつまいもの由来
さつまいもの原産地は南米といわれています。
長年かけて世界中に広まったとされていますが、南米からフィリピンに伝わり、1500年代後半にフィリピンから中国に伝わりました。
フィリピンで栽培されたさつまいもの持つ栄養が穀物に匹敵する食材であることに驚き、中国人の陳振竜が、甘藷のつるを船の舳綱に巻いて、ひそかに持ち出したといわれています。
持ち出した甘藷を、陳は金学曹という地方役人をしている人に献上し、飢えに苦しむ人びとを救うために甘藷の栽培を国中に広めていきました。
そして1600年頃日本に中国からさつまいもがやってきました。
さつまいもを漢字で「薩摩芋」と書きます。
さつまいもという名の由来は、、1600年ごろ、琉球(今の沖縄県)から薩摩(今の鹿児島県)に伝わったものなのです。
2.他にもある!さつまいもの呼び方
2-1.甘藷
薩摩芋の中国名で「甘藷(カンショ)」と呼ばれることも多いです。「甘い芋」を意味しています。
薩摩芋の次に聞き覚えのある名称ですよね。
2-2.唐芋
中国(唐の国)から伝わってきた芋というのが由来で「唐芋(カライモ、トウイモ)」とも呼ばれています。
2-3.琉球芋
琉球(今の沖縄県)から伝わった芋という意味で「琉球芋」とも呼ばれていました。国や地域の名前が由来になることが多いようです。
2-4.十三里
江戸時代に入り、徐々に栽培地域が広まってくると、甘くて美味しいさつまいもを、栗より美味しい芋として「十三里」と呼んでいました。
焼き芋は江戸にも伝わり、焼き芋屋さんが、「十三里」と名付けたところ 「栗(九里)より(四里)うまい十三里」という洒落が江戸っ子に評判を生み、それから「さつまいも=十三里」となったようです。
さつまいもを「十三里」と呼ぶことから、1987年に埼玉県川越市の「川越いも友の会」が、旬にあたる10月13日を「さつまいもの日」としています。
まとめ
さつまいもにもいろいろな漢字、呼び方があったんです。
輸入先の地名で呼ばれることが多かったようですね。
昔からさつまいもは必要とされており、色んな国や人々に愛されていたことがわかりました!
「大学いも」という名前の由来は?諸説ある名前の由来や大学いもの起源を解説!
カリッとした食感がよく、甘くておいしい大学いも。
おやつだけではなく、食事やお酒のおつまみとしても人気ですが、なぜ大学いもという名前なのだろうと一度は思ったことがあるのではないでしょうか?
今回は大学いもの名前の由来や起源などをくわしくご紹介します。
1.諸説ある大学いもの名前の由来
1-1.最も有力な大学生に人気だったから説
大学いもの名前の由来として一番有力といわれている説は、大学生に人気だったからといわれています。
今も昔も年齢問わず人気の大学いもですが、とくに好んでいたのが東京の学生街にいる大学生たち。
大正から昭和にかけての大学生は、ほとんどがお金のない苦学生でした。そのような苦学生でもさつまいもは安価で購入しやすく、お腹を満たせる食材だったのです。
学生街は、神田や高田馬場付近などいくつか候補がありますが、一番有力なのは東大赤門前ではないかといわれています。
1940年ころにあった三河屋というお店で、さつまいもを揚げて蜜をかけて売っていたという情報があるからです。
1-2.大学生が学費のために売っていたから説
大学生が学費を稼ぐために売っていたからという説も。
不況で学費を払うのが苦しくなった大学生たちが、安く手に入るさつまいもと砂糖を使用して開発し、売り始めたのが名前の由来ともいわれています。
1-3.商品名に「大学」を付けるのが流行だったから説
大正時代から明治時代にかけて、商品名に「大学」を付けることがブームになりました。実は今でもある「大学ノート」も流行りにのって名付けられたもの。
大学いももその流行りにのってという説があります。
2.大学いもの起源は中華料理から
名前の由来は諸説ある大学いもですが、レシピは「ミーチェンホンシュー」や「バースーバイシュー」という中華料理からといわれています。
作り方はほとんど同じですが、これらの中華料理と大学いもの違いとして、大学いもにはゴマがふりかけられているのが違いとしてあります。
3.実は「中学芋」と「小学芋」も存在している
3-1.中学いもとは
中学いもは、大学いもを小さくしたもの。大学いもは乱切りや輪切りなどで比較的大きいサイズですが、中学いもはサイコロのように正方形で小さいのが特徴です。
3-2.小学いもとは
小学いもとは、料理ブロガーである山本リコピンさんの娘さんが考案したレシピ。
スティック状にカットしたさつまいもを油で揚げて、青のりと塩をまぶしたものになります。
さつまいもを使ったこと、娘さんが小学生だったことから、小学いもと名付けたのだそうです。
4.大学いもに関するQ&A
4-1.大学いもと中華ポテトの違いとは?
中華ポテトは関西地域での大学いもの呼び名です。
関西の中華料理店には中国出身の料理人が多かったため、ミーチェンホンシューの作り方が持ち込まれ、徐々に家庭にも広がったといわれています。
4-2.大学いもと芋けんぴとの違いとは?
芋けんぴは、さつまいもを揚げて蜜をかける工程は一緒ですが、細くスティック状になっており、大学いものような柔らかさはありません。
芋けんぴは高知の名物で、小麦粉で作る焼き菓子のけんぴと似ていることから名付けられました。
今では全国のスーパーやコンビニなどのお菓子コーナーにも売っています。
まとめ
大学いもの起源は中華料理ですが、大学生が好んでいた、大学生が売っていたなど、名前の由来ははっきりしていません。
また、大学いもは地域によって呼び名が変わる不思議な料理です。
諸説ありますが、名前の由来に大学生がかかわっていることは間違いなさそうですね。
さつまいもを焼き芋にするとなぜ甘くなる?さつまいもの甘さの理由とおすすめ品種を紹介!
皆さん、甘い焼き芋はお好きですよね!でも「なぜ焼き芋が甘いのか」その理由をご存知でしょうか?
実はさつまいもをただ焼くだけでは甘くならないのです。焼き芋が甘くおいしくなるためには「熟成」「酵素」「品種」の大きな3つの理由があります。
その理由を知って、甘くておいしい焼き芋を楽しみましょう!
1.さつまいもを焼き芋にすると甘くなる3つの理由
1-1.熟成貯蔵で甘くなる
実は、収穫したばかりのさつまいもはあまり甘くありません!
収穫したさつまいもを冷暗所で約1カ月間ほど常温保存することで、さつまいもは熟成されより甘くなります。
掘りたてではなく熟成されたさつまいもを使うこと。これが甘い焼き芋にするために欠かせないポイントのひとつです!
家庭で熟成させるには、
土がついたまま半日~3日ほど陰干しして乾燥させる(水濡れ厳禁!)
1本1本新聞紙にくるんで段ボールに入れる
冷暗所(10~15℃がベスト)で1カ月ほど保管する
こうすることで、ご自宅でも簡単に追熟させることができます!
この方法はさつまいもを長持ちさせる保存方法でもあるので、覚えておいて損はないですよ。
1-2.β-アミラーゼの活性で甘くなる
さつまいもに含まれているβ-アミラーゼという酵素は、約70℃で一番活発に働き、さつまいものでんぷんを麦芽糖に変えて甘くしてくれます。
β-アミラーゼの活動が一番活発になる温度帯を時間をかけて通り過ぎると、酵素がより長く働き、多くのでんぷんが糖に変わって焼き芋が甘くなります!
焼き芋はβ-アミラーゼの活動が一番より活発になる約70℃の温度帯でじっくり焼くのがオススメです!
1-3.品種による糖度の違い
紅はるかや安納芋などは生の状態でも糖度が高い品種です。これらのさつまいもを焼き芋にすることで、「砂糖が入っているのでは!?」と疑うほどの甘さの焼き芋を味わうことができます。
しかしさつまいもには他にも、しっとり甘い品種やホクホクした美味しさの品種などいろいろな品種があります。
それぞれに違ったおいしさの特徴があるので、次の見出しでイチオシの品種を詳しくご紹介しますね。
2.甘さが特徴的なさつまいもの品種5選
2-1.紅はるか
甘さが特徴的な品種の代表格の紅はるか。
焼き芋にするとねっとり甘くなり、その糖度はなんと50~60度にもなります。これはほぼガムシロップの糖度と同じ。甘いと有名なあの安納芋を超えるともいわれています。
とにかくねっとり甘いスイーツのような焼き芋が好みの方には大変オススメです!
2-2.安納芋
甘いさつまいもと言えば、高い知名度を誇る安納芋。
こちらも焼き芋にすると、蜜があふれてねっとり甘くなります。糖度も紅はるかに近い40度ほどの糖度があり、甘くておいしいです!
さつまいもの多くは中身が黄色に近い色ですが、安納芋は中身がオレンジ色をしています。
2-3.シルクスイート
シルクスイートはしっとりとした上品な甘みと、ねっとりし過ぎないなめらかな舌触りが特長の品種。
あまりスーパーには出回っていないため、知名度はあまり高くありませんが近年注目されている品種です。ネットなら簡単に手に入ります。
上品な甘さとなめらかな舌触りの焼き芋を試してみたい方にオススメです!
2-4 紅あずま
王道の紅あずまは一番流通している品種で、特に関東で幅広く人気があります。
昔からよく食べられており、「焼き芋といえば紅あずま」をイメージされる方も多いのではないでしょうか。
甘さでは上記の3品種にはかないませんが、ほどよい甘さとホクホクとした食感が特長で、焼き芋だけでなく料理にも向いている万能の品種です。
2-5 鳴門金時
鳴門金時は、徳島県を原産とし主に関西地方で幅広く食べられているさつまいもです。
東の紅あずまと並んで焼き芋の元祖とも言われる鳴門金時。
ねっとり系よりもホクホク系が好きという方におすすめです!こちらも天ぷらなどの料理にもピッタリです。
3.焼き芋の甘さが足りない時は?
さつまいもを焼き芋にして、いざ食べてみたらあんまり甘くなかった…という経験はありませんか?
そんなとき「もっと甘い方がよかったけれど仕方ない…」と諦めてしまう方も多いと思います。
でもちょっとした工夫であんまり甘くない焼き芋を救済できちゃうんです!
ここでは超簡単にイマイチ焼き芋をおいしくする方法をご紹介します!
3-1.バターorマーガリンをつける
じゃがバター、おいしいですよね。同じいも類のさつまいもなら、合わないわけがありません。
やはり焼き芋とバター(マーガリン)の相性は抜群!
バター(マーガリン)のいい感じの塩味がさつまいもとよく合います。
アツアツの焼き芋にバター(マーガリン)をつけて染み込ませる…。これだけでおいしさがレベルアップします!
3-2.アイスを添える
焼き芋にバニラアイスを添える食べ方がオススメ!
焼き芋のホクホク感に、バニラアイスのなめらかな甘みがマッチしてとてもおいしいです。ホカホカとひんやりの温度差も楽しいおやつにピッタリな組み合わせ。ぜひ試してくださいね!
3-3.チーズを乗せる
実は、焼き芋にチーズ(とろけるタイプ)を乗せて焼くと、これまたおいしくなります!
アツアツの焼き芋に乗せるだけなので気軽にできますよね。
チーズの塩気がさつまいもが持つ甘みを引き立たせてくれます。
3-4 はちみつをかける
純粋に甘みをプラスできるはちみつ。
普通の砂糖をかけるよりも断然オススメです。
はちみつは砂糖に比べ栄養価が高く、血糖値の上昇もゆるやか。また少ない量でも甘くなるので、摂取カロリーも少なくてすみます。
特に健康に気を付けている方やダイエット中の方にオススメの方法です!
4.市販のさつまいもで甘いものを選ぶためのポイント
4-1.皮の色が濃く、ツヤがある
皮の色が濃く、ツヤがあるものがGOOD!
健康に育ったおいしいさつまいもの証です。
ただ安納芋など、元々皮の色が薄い品種もあるので注意してください。
4-2 形が適度に太く、先に向かって細くなっている紡錘形(ぼうすいけい)のものを選ぶ
形は適度に太く、レモンのように先に向かって細くなっている紡錘形(ぼうすいけい)のものを選んでください。
そして持った時にずっしり重く、表面のくぼみが浅いさつまいもがオススメです!
安納芋の場合は、卵よりも一回り大きいくらいの大きすぎないものがGOOD。こちらもずっしりとした重みがあるものを選びましょう。
4-3 端の切り口で選ぶ
切り口に蜜が出ている・蜜が乾いて黒くなった跡があるものがオススメ。知らないと「汚れているのかな?」と思ってしまうかもしれません。
しかし蜜が出ているさつまいもは甘くておいしい証拠です!
5.甘い焼き芋を作る方法
おうちで簡単にできる甘い焼き芋の作り方をご紹介します。
甘い焼き芋は低温で長い時間かけてじっくり焼くことが最も重要。気長に待ちましょう!
5-1.オーブン|入れっぱなしで簡単
①さつまいもをアルミホイルで包み、160℃のオーブンで90分ほど焼きます。
②甘い香りがたち、竹串を刺せる柔らかさになったら甘くておいしい焼き芋の完成です!
https://oimobicho.jp/basic/yakiimo-oven/
5-2 電子レンジ|時間がないときの強い味方
①さつまいもを濡らしたペーパータオルで包み、その上からラップで包みます。
②それを電子レンジ(500W)で1分加熱した後、150Wで15分程度加熱して完成!
https://oimobicho.jp/recipe-column/yakiimo-microwave/
5-3 フライパン|香ばしさをプラス
①洗ったさつまいもを濡れたままアルミホイルに包み、フライパンに並べます。
②蓋をして弱火で20分、裏返して20分焼きます。
③甘い香りがして竹串が刺せる柔らかさになったらおいしい焼き芋の完成です!
https://oimobicho.jp/recipe/easy-baked-sweet-potato-in-a-frying-pan/
まとめ
さつまいもの定番の食べ方「焼き芋」。この焼き芋が甘いのは当たり前ではありません。
熟成・酵素・品種のすべてがそろうことで、とっても甘くておいしい焼き芋になるのです。
紅はるかや安納芋、シルクスイートは他の品種に比べ、ねっとり・しっとりとした圧倒的な甘さを誇ります。しかし昔ながらの紅あずまや鳴門金時も、王道のホクホク感が楽しめ根強い人気です。
買うときに甘いさつまいもを見極め、できるだけ長時間じっくり焼くことでより甘い焼き芋ができあがります。
もしも作った焼き芋があまり甘くても、あきらめずに一工夫してみましょう。意外な発見があるかもしれません。
大人から子どもまで大好きな甘い焼き芋。甘さの理由やコツを知って、あなたの好みを見つけてみてくださいね!
「甘藷」って何?「甘藷」の読み方や甘藷を使ったおすすめレシピを紹介
教科書などで出てきた「甘藷」という言葉。何と読むかご存知でしょうか?
中々馴染みの無い言葉ですが、実はとっても身近な食材の名前なんです。本日は「甘藷」とは何かについて解説します。
1.甘藷とは
「甘藷」の読み方は「かんしょ」で、実は漢名で「さつまいも」を表す言葉なんです。
さつまいもは1,600年頃に中国から沖縄へと伝えられ、当時は「甘藷(かんしょ)」や「唐芋(からいも)」と呼ばれていました。
甘藷は「甘い芋」を意味し、唐芋は「唐(中国)から伝わった芋」としてその名が付けられています。
その後、青木昆陽が薩摩地方から甘藷を取り寄せたことで、「薩摩(さつま)から伝わった芋」として「さつまいも」の名称が誕生したのです。青木昆陽は甘藷=さつまいもを普及した人物として、「甘藷先生(かんしょせんせい)」と呼ばれていたんですね。
2.日本以外でのさつまいもの表現
日本ではさつまいもは「甘藷」「唐芋」などと表現されることもありますが、日本以外ではどのような呼び方がされているのでしょうか。
英語ではさつまいもはSweet potato(スウィート・ポテト)、フランス語では patate douce(パタートゥ・ドゥース)、イタリア語では patata dolce(パタータ・ドルチェ)と呼ばれており、いずれも「甘いジャガイモ」を意味しています。
さつまいもを英語でSweet potatoと表現するのであれば、スイーツでおなじみのスイートポテトはどう表現するの?と思われるかもしれませんが、英語でスイーツのスイートポテトは「sweet potato cake」や「sweet potato tart」などと表現されます。
3.甘藷の品種
世界には、3,000~4,000種もの甘藷が栽培されていると言われています。その中でも日本で栽培されているのは約60種類。
やきいもブームの火付け役!ねっとり食感の「安納芋(あんのういも)」や、ホクホク食感が特徴の「鳴門金時」、しっとりとした食感の「紅はるか」などはスーパーなど身近な所でも見かけることが多いのではないでしょうか?
産地や農園によって、旬の時期や色味、食べたときの食感も異なります。たくさんの品種を食べ比べて、自分のお気に入りの甘藷を見つけてみて下さいね。
美味しいさつまいもの品種は下記の記事で紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。
甘いさつまいもの品種はこれだ!イチオシの品種とさつまいもの見分け方
4.甘藷のおすすめレシピ
甘藷はおかずからおやつまで出番は様々。
甘藷を使ったレシピはこちらで紹介しているので、ぜひさまざまなレシピを参考にしてみてください!。
おいも美腸研究所 レシピページ
まとめ
以上、本日は「甘藷」の読み方、そして甘藷を使ったおすすめのレシピを紹介させて頂きました。
スーパーに並ぶさつまいもも、よく見ると「甘藷」という名前で表現されていることがあるかも・・・?
身近な食べ物であるさつまいもですが、「甘藷」と呼ばれている場面を是非身近なところでも探してみて下さいね。
蜜たっぷりのさつまいも「蜜芋」が食べたい!おすすめの蜜芋の品種と入手方法を解説
秋を迎えると食べたくなるのが蜜がたっぷりの甘いさつまいも。夏場から冷やして食べるやきいもに引き続き、秋はもちろん温かいやきいもが食べたい季節!
ホクホクのさつまいももいいけど、しっとりした蜜がたっぷり詰まった甘ーいやきいもを食べたいなと思う方におすすめ!
蜜がたっぷり詰まったさつまいも『蜜芋』をご紹介します!!
1.蜜たっぷりのさつまいもについて知ろう
1-1.「蜜芋」と普通のさつまいもは何が違うの?
蜜芋とはやきいもにした時に芋の中に蜜が入っているかのように、水分量が多く糖度が高いものを指します。
その食感は普通のさつまいもとは異なりしっとりとしていて甘みが強いのが特徴です。
蜜芋にはいろいろな品種があり、近年も新しい品種が開発されていますが、代表的なものに安納芋や紅はるかなどがあります!
1-2,さつまいもの「蜜」の正体は水飴の成分
さつまいもを焼いた時にたっぷりの蜜が出るのには秘密があります。
まず、蜜ができる仕組みがさつまいもに含まれるデンプンがベータアミラーゼという酵素によって水あめの主成分である『麦芽糖』と呼ばれる糖に変換されることで蜜ができます。
これは、すべてのさつまいもで出来るわけではなく、さつまいもに含まれる酵素の力とその酵素が発揮できる温度帯で焼いてあげること、さらに生芋の段階での熟成技術があってこそ蜜が出るようになります。
2.蜜たっぷりのさつまいも|おすすめの品種3選
2-1.蜜芋の代表格|安納芋
安納芋は蜜芋ブームの火付け役と言われるほど代表的な品種です。
その甘さは焼き芋にすると糖度が40度を超えるような甘さで、これは完熟マンゴーが糖度20前後なのでそれをはるかに上回るほど甘い品種なのです!
安納芋は『安納紅(あんのうべに)』と『安納黄金(あんのうこがね)』と呼ばれる2つの品種の総称で、皮が赤いほうが『安納紅』、白っぽいほうが『安納黄金』です。
世間に流通するほとんどが安納紅の方なので安納芋=安納紅のイメージで定着したようです!
安納黄金は安納紅よりも水分が低く甘さをより感じることができるので、ぜひ安納黄金もお試しください!
2-2.安納芋をも超える甘さ!?|紅はるか
蜜芋ブームで人気沸騰中の品種が『紅はるか』です。
紅はるかの名前の由来は「はるかに甘いさつまいも」からきているくらいかなり甘いのが特徴です。
生育と熟成と焼成のバランスがベストだと安納芋の甘さをも上回る糖度を持つ品種です。
安納芋と同様にねっとり系に分類される品種なので、蜜芋ブームの中でも引けを取らない味わいです。
2-3.なめらか食感がたまらない|紅まさり
紅まさりは関東を中心とした地域での栽培が盛んで、シルクスイートの原種となった品種です。
さつまいも本来のホクホク感は残しつつ、しっとり感を兼ね備えた口当たりが滑らかなのが特徴です。
身がキレイな黄色で甘さも程よい甘さで、さつまいも本来の味わいを楽しむことができます。
3.蜜たっぷりのさつまいもを手に入れる方法
3-1.スーパーで購入する|おいしい安納芋の見極め方
ここで、おいしい安納芋の見極め方をお教えします!
・中くらいの大きさの丸いもの
・ずっしりと重みのあるもの
・端の切り口から蜜が出ているもの
・皮の色が濃くつやのあるもの
・傷がなくきれいな皮のもの
以上のポイントを押さえることがおいしい安納芋を選ぶコツです!
3-2.通販を利用する
らぽっぽファームオンライン 厚切りカット甘熟紅はるかやきいも
さつまいものお菓子で有名ならぽっぽのオンラインで買える商品。
カットされている冷凍のやきいもなので、食べてい時に食べたい分だけをすぐに食べることができる商品でした!
焼き芋って1本で売っているからなかなか画期的な商品ですね!
商品サイトはこちら↓
紅はるか使用! 甘熟美腸やきいも
まとめ
今流行りの蜜芋の仕組みはいかがでしたでしょうか?
蜜芋になるためには、どんなさついもでも成ることが出来るわけではないので注意が必要です。
通販で生芋もたくさん売っていますが、らぽっぽさんの冷凍やきいもはそのまますぐに食べることが出来るのでおすすめです!
是非、いろんな品種をお試しください。
王道ねっとり系さつまいも4選!ねっとり系さつまいもで作るおいしい焼き芋の作り方も解説
昔ながらのホクホク系さつまいもを超えて、近年大人気のねっとり系さつまいも!
今回はその中でも特に人気の高い4つの品種について取り上げました。さつまいもがねっとり風になるやきいもの作り方もご紹介♪
1.ねっとり系さつまいもの王道品種4選
1-1.ねっとり系さつまいも代表「安納芋」
水分が多くねっとりとした食感の代表格ともいえる人気のさつまいも。鹿児島の種子島安納地方から広まったのが名前の由来と言われています。
調理すると鮮やかで濃い黄色になり、焼き芋にすると蜜が出てくるほど甘いので「蜜芋」の別名も持っていて、生の状態では糖度16度程で、加熱すると40度近くにまで糖度は高くなります。
1-2.安納芋にも負けない甘さの「紅はるか」
紅はるかは2010年に品種登録された品種。味、見た目などが従来の品種よりも「はるか」に優れるということが名前の由来です。
クリーミーで安納芋にも負けない甘さを持っていますが、後味がすっきりしているのが特徴。加熱後の糖度は安納芋を超える50~60度程にもなるすごく甘いさつまいもです!
1-3.上品な食感がたまらない「シルクスイート」
シルクスイートは2012年に登場した品種。上品な甘さと絹のように滑らかな食感が特徴のシルクスイート。
ねっとり系ほっこり系に続く新しい食感のしっとり系とも呼ばれています。
採れたてだとホクホク系に近いのですが、時間をおいて寝かせるとねっとり系の食感になるという、二つの顔を持つのも特徴です。
1-4.わりと最近登場した品種「クイックスイート」
ベニアズマに九州30号を交配して作られた、新しい品種がクイックスイートです。品種登録されたのは平成17年と比較的最近。
生のままだと糖度16度、しかしレンジなどで加熱すると糖度38度まで甘くなります。
2.ねっとり系さつまいものおいしい食べ方
2-1.王道の「焼き芋」
さつまいもといえば、やっぱり焼き芋です。
焼き芋は低温(70℃~80℃)でじっくりと加熱することでさつまいもの中のでんぷん質が糖へと変化していきます。
さつまいもがもつ甘さを十二分に味わうことができて、皮ごと食べることで栄養をまるごと取り入れることができます。
2-2.甘みがさらに濃縮「干し芋」
干し芋は蒸したサツマイモをスライスして4日ほど天日干しをして作ります。
ねっとり系さつまいもで作った干し芋は水分が少なくなることでよりねっとりとした噛み応えが増し、甘みもぐっと濃縮されます。
手軽に食べられるのも干し芋のいいところですね。
2-3.絶対外さない「スイートポテト」
さつまいものスイーツといえばスイートポテト。
蒸したさつまいもをつぶして裏ごしし、砂糖、牛乳、バターを混ぜてオーブンで焼き上げて作る、日本生まれの洋菓子です。
https://oimobicho.jp/recipe-column/easy-sweet-potato-sweet-recipe/#4_25
3.ねっとり系になる焼き芋の作り方3選
3-1.オーソドックスなレンジを使った焼き芋レシピ
自宅にある電子レンジは立派な調理器具!簡単に焼き芋を作ることができます!
よく洗ったさつまいもをキッチンペーパーで隙間なく包んでその上からラップで軽く包みます。
200Wで10分から15分ほど電子レンジで加熱し、竹串が通るようなら完成です!
レンジごとで加熱時間は多少変わりますので、適宜調整してください。
レンジでねっとり風にするポイントは、ラップをふんわり巻くこと!こうすることでラップとの間に蒸気が篭り、蒸し焼きのような効果が得られます。
https://oimobicho.jp/basic/yakiimo-microwave/
3-2.オーブンを使った本格的な焼き芋レシピ
より本格的に作るならオーブンがおすすめです。
よく洗ったさつまいもを湿らせた新聞紙もしくはキッチンペーパーでしっかり包み、その上からアルミホイルで包んで160℃~180℃に設定したオーブンで60分から90分焼きます。
余熱はいりませんので、天板に乗せてスイッチを押すだけの簡単手順で本格的な焼き芋が楽しめます!
ポイントは加熱後は10分から15分ほどオーブンに入れたままにしておくと余熱でじっくり熱が通り、ねっとり風に仕上がります。
https://oimobicho.jp/basic/yakiimo-oven/
3-3.実は優秀!炊飯器を使った焼き芋レシピ
意外と知られていないですが、炊飯器で焼き芋ができるんです。
やり方も簡単!炊飯器に洗ったさつまいもといもの半分くらいの水を入れて炊飯ボタンを押すだけ!
また玄米炊飯などの炊飯モードを変えると食感も変化するのでお気に入りの作り方を自分で探してみましょう!
ポイントは炊飯器の保温の温度は、でんぷんが糖へと変化する70℃台でキープされます。
炊飯が完了した後さらに保温で10分以上置いておくと、よりねっとり甘い焼き芋に仕上がります!
まとめ
さつまいものねっとり感を味わうには「低温でじっくり焼く」がポイント!
オーブンだけでなく電子レンジ、炊飯器でも手軽に調理できるので、是非試してみてください!
アツアツの焼き芋で心もおなかも温かくしていきましょう。
大学芋は太る食べ物?ダイエット中に食べても大丈夫?大学芋のカロリーについて解説!
おやつにはもちろんのこと、お酒のおつまみやおかずにもなる大学芋ですが、さつまいもを揚げてから砂糖を使用するため、カロリーが気になるところ。
大学芋が大好きでも「太るのではないか?」と考えてしまい、ダイエット中で控えている人もいるでしょう。
そこで今回は、大学芋のカロリーや太りにくい大学芋を作るコツなどをご紹介します。
1.大学芋のカロリー
大学芋の100gあたりのカロリーは231 kcal。
アイスクリームやシュークリームとくらべると少し高いですが、あんこや生クリームがたっぷりと使われている大福やショートケーキなどよりは少なくなっています。
商品名
カロリー(100gあたり)
大学芋
231kcal
アイスクリーム
180kcal
シュークリーム
197kcal
大福
242kcal
ショートケーキ
308kcal
(情報参考元:カロリーSlism)
2.大学芋はダイエット中に食べても大丈夫?
大学芋はダイエット中に食べてもOKですが、カロリーが高いため食べ過ぎは厳禁。しかし、1日に小鉢1皿分程度であれば食べても問題はありません。
なぜなら大学芋は腹持ちが良く、栄養豊富。お通じの改善に役立つ食物繊維やヤラピン、むくみ解消に効果が期待できるカリウム、糖質の代謝を促してくれるビタミンB1など、ダイエットにもうれしい栄養がたくさん含まれています。
自分で大学芋を作る場合、ちょっとした工夫をするだけで、通常よりカロリーを抑えることができます。作り方のポイントは次の項目で見ていきましょう。
3.大学芋のカロリーを抑える作り方のポイント
3-1.さつまいもを揚げないで作る
本来、大学芋は油で揚げるのが主流ですが、自宅では油の量を減らし、揚げ焼にするとカロリーがぐっと抑えられます。電子レンジで加熱してもいいですね。
また、皮付きのまま調理すると、より多くの食物繊維を摂取できます。
3-2.砂糖をパルスイートに替える
大学芋の糖蜜にパルスイートなどの甘味料を使用することで、カリカリの食感を残したままカロリーを抑えることができます。
パルスイートは砂糖の3分の1程度の量でOK。ダイエット中に活躍してくれる調味料です。
3-3.大学芋の密の量を少なくする
パルスイートなどがない場合、単純に糖蜜を少なくすることで、カロリーオフが可能です。
糖蜜の量によっては、カリッとした食感があまりないかもしれませんが、さつまいも自体の甘さを感じることができますよ。砂糖の甘さだけではなく、素材の味も楽しんでみてくださいね。
まとめ
大学芋は揚げた後に砂糖も使用することから、カロリーが高く太るのではないかというイメージが強いですが、摂取量に気をつければダイエット中に食べても問題ありません。
さつまいもは腹持ちがよく栄養も豊富で、ダイエットにも効果が期待できる食物繊維やビタミンなどが含まれています。
「大学芋が好きだから、少し多めに食べたいな…」と思っている人は、自宅で作るのがおすすめ。たっぷりの油で揚げるのを控え、砂糖の種類や量に注意しましょう。
さつまいもの病気の種類や、発病したときの対策方法!
大切に栽培してきたさつまいも、気が付いたら病気になっていた!なんてこともありますよね。
さつまいもを栽培する上でも対策がとても重要になってきます。
甘くておいしいさつまいもを収穫するためにも、病気や害虫対策を把握しておくことがとても大切になります。
そこで今回は、さつまいもの病気や害虫、対策方法についてご紹介します!
1.さつまいもが病気になったときに現れる症状
1-1.葉の色が褐色になる
褐色(かっしょく)とは、黒みを帯びた濃い茶色のことをいいます。葉の色がこのような褐色になってしまった場合は病気に感染している可能性があります。
1-2.葉に穴が空いてしまう
もっとも多いのが、葉っぱが穴だらけになってしまう症状です。葉っぱの穴は害虫の存在を示してくれる証拠です!
放置をしておくと大半の葉っぱがなくなってしまう可能性もあるので、まずは対策をしましょう。
1-3.株がしおれる
株がしおれるといった症状がみられる場合は、土壌病害の可能性があります。そのままにしてしまうと、生育不良となり枯死してしまう事もあるので早期対策が必要です。
1-4.葉が枯れてしまう
元気だった葉が枯れてきてしまうのは、立ち枯れ病の可能性が考えられます。急激に生育が衰えてきてしまうので、早い段階で対策を取らなければいけません。
1-5.白いカビが生える
葉の表面に白い粉のようなカビが見られる場合は、うどんこ病の可能性が考えられます。
放置してしまうと、葉の表面全体が真っ白になるまで繁殖してしまうので早めに対策を取りましょう。
2.さつまいもの病気の種類
2-1.うどんこ病
うどんこ病とは、名前の通り白い粉のようなカビが生えてしまう病気です。
葉っぱの表面に繁殖するため放置してしまうと葉っぱ全体が真っ白になってしまい、葉や茎が奇形になってしまったり枯れてしまう事もあります。
2-2.つる割れ病
つる割れ病は、日中は下葉がしおれてしまい、夜は元に戻るといったことを繰り返し、最後には株全体がしおれてしまいます。
そのままにしてしまうと株元の茎が割れてきてしまい、カビの発生原因にもなってしまいます。
2-3.立ち枯れ病
立ち枯れ病は、下葉が黄化してしまいしおれ始めます。そのまま進行してしまうと株全体が枯れてしまいます。
最後には根や茎が腐敗してしまう可能性があります。
3.さつまいもの病気の原因
3-1.糸状菌による土壌病害
つる割れ病や立ち枯れ病の主な原因となるのが、糸状菌による土壌病害です。
糸状菌はカビの一種で、この病原菌が土壌から伝染してしまいさつまいもの根から侵入してきてしまうのです。
病原菌の土壌殺菌消毒が不十分といえる証拠なので、きちんと対策をしなければいけません。
3-2.害虫病害
さつまいもには、いくつもの害虫病害がみられます。主に原因となっている代表的な害虫をご紹介します。
アブラムシ
アブラムシは代表格とも言える害虫です。葉や茎などに群棲し、植物の汁を吸って生育を阻害してしまうのです。
また、新芽や若葉などに発生することが多く繁殖をしてしまうので注意が必要です。
コガネムシ
コガネムシは成虫、幼虫共にさつまいもに被害を与えてしまう害虫です。
幼虫は地中で根を食害し、枯れさせてしまいます。成虫は葉を食い荒らしてしまうのです。
サツマイモネコブセンチュウ
センチュウは緑虫とも言われ、土の中のあちこちに棲んでいます。
センチュウは口針で根に穴をあけ中に侵入します。そのためセンチュウが寄生してしまうと、しおれや枯れてしまうといった状態になってしまうのです。
ハリガネムシ
ハリガネムシは幼虫による食害が主になります。名前の通り針金が貫通したような痕を残すのが特徴です。
そのままにしてしまうと食害が広がり、さつまいもの奥深くまで穴ぼこだらけになってしまいます。
3. さつまいもの病気や害虫対策
3-1.病気を防ぐための対策
さつまいもがつる割れ病や立ち枯れ病など、病気にならないためにも、あらかじめ対策が必要になります!
まずは健全苗を確保し、発病圃場の種いもは使用しないように気を付けましょう。
植え付け前は苗の消毒を十分行うことが大切です。不十分であることから土壌病害に繋がってしまうのです。
3-2.病気になってしまったら
病気にかかってしまったら、まずは発病してしまった葉や根を早めに切り取って処分をしましょう。
病気によっては伝染してしまう恐れがあるので、殺菌剤などで速やかに治療を行いましょう。
3-3.害虫を防ぐには
害虫はどうしてもやってきてしまうので、最大の悩みでもありますよね。
害虫を見つけたり、食害痕を見つけた場合は早急に殺虫剤や薬剤散布を行いましょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか、さつまいもにもさまざまな病気が存在します。まずは病気の素となっている原因をしっかりと把握し、対策をとることが大切です。
愛情を注ぎ大切に育てているさつまいもだからこそ、こまめにチェックをしておきましょう!
また、
「家庭菜園や自分の畑以外でのさつまいもの収穫や栽培の体験がしてみたい」
「違う場所で体験して今後に栽培に活かすための参考したい」
という方にピッタリなおすすめスポットがあります!
それがなめがたファーマーズヴィレッジ。
こちらでは、さつまいもの収穫のプロと、さつまいもの収穫体験が出来るイベントを毎年秋に開催しています!
実際の栽培の状況を見ながらプロと一緒に収穫ができるので、家庭菜園や自分の畑だけでは難しい貴重な体験ができますよ。
詳しくはこちら。
↓↓↓↓↓↓↓
さつまいものつるを有効活用!さつまいものつるは捨ててしまうのがもったいないほど魅力がたっぷり
さつまいもは家庭菜園でも簡単に育てることができ、人気の作物ですが、さつまいもを育てた後、収穫の際につるの処理に困る方も多いと思います。
ごみとして捨ててしまう前に、実は活用できる方法があるんです!
今回は、さつまいものつるの活用方法をご紹介したいと思います!
1.さつまいもの収穫時のつるの処理方法
1-1.土に埋める
さつまいものつるは土に埋めると栄養になるのでおすすめです。
そのまま埋めてもいいのですが、1週間~2週間ほど天日干しで乾かしてから土に埋めると、水分が減ってかさも減るので混ぜ込みやすくなります。
どうせ捨ててしまうなら次に作物を作るときの栄養にしてしまいましょう!
1-2.調理して食べる
さつまいものつるは、調理して食べることができます。
つるには、さつまいものいもの部分と同様に食物繊維と水溶性ビタミンが含まれています。
いもだけではなく、つるも食べることができるのは一石二鳥ですね!
2.さつまいものつるを使ったレシピ2選
2-1.さつまいものつるのおひたし
材料
さつまいものつる 長さ10cm程度のものを10本ほど
塩 1つまみ
しょうゆ 大さじ1
和風だし(顆粒) 小さじ1
酒 大さじ1/2
さつまいものつるのおひたしの作り方
①鍋に湯を沸かし、沸騰したら塩を入れる。
②さつまいものつるを3~4cmほどに切り、1分~1分半ほど茹でる。
③お湯からあげたら、冷水で締める。粗熱がとれたら、水分をなるべく絞り、キッチンペーパーで水分を拭き取る。
④しょうゆ、和風だし、酒を混ぜて、そこに③を浸す。
⑤皿に盛って完成!
作り方のコツ
お湯からあげたときにすぐに冷水で締めるのと、④で長くつけすぎないことがポイントです!
味が濃くなりすぎないように、サッとからめたらすぐに引き上げましょう。
2-2.さつまいものつるのきんぴら
材料
さつまいものつる 長さ10cm程度のものを10本ほど
ごま油 適量
★しょうゆ 大さじ1と1/2
★みりん 大さじ1
★酒 大さじ1
★砂糖 大さじ1
★唐辛子 1ふり
さつまいものつるのきんぴらの作り方
①さつまいものつるの皮を剥いて、水につけてのアク抜きをする。
②さつまいものつるを3~4cmに切る。
③フライパンにごま油を入れて、水を切ったさつまいものつるを強火で1分炒める。
④強火のまま①を加えて、焦げないように混ぜながら水分を飛ばす。
⑤水分がなくなってきたら火を止めて、盛り付けて完成
作り方のコツ
さつまいものつるにもさつまいも同様アクがあるので、皮を出来る限り剥いて水にさらし、アク抜きしてからきんぴらにすることがコツです!
さつまいものつるのきんぴらの作り方を写真付きで解説!
https://oimobicho.jp/recipe/kinpira/
まとめ
さつまいものつるは取り除いたら雑草のように使い道がないと思われがちですが、さつまいものつるは有効活用ができます。
肥料として土に埋めるときは、1週間~2週間ほど天日干しで乾かしてから土に埋めると、水分が減ってかさも減るので混ぜ込みやすくなります。
また、調理をして食べることもできるので、ぜひレシピを参考にしてみてください。
さつまいもでダイエット?さつまいもダイエットの効果ややり方やおすすめレシピを解説!
さつまいもはダイエットに効果的と聞いたことがある人もいるのでは?
ご飯などの主食の代わりにさつまいもを取り入れることで、痩せる効果が期待できると話題になっていますが、さつまいもは甘いのでカロリーや糖質が高いイメージですよね。
おいしいさつまいもで無理なくダイエットができるのであれば、取り入れてみたいと考える人も多いでしょう。
今回は、さつまいもダイエットの正しいやり方と、具体的にどのような効果が期待できるのかなどくわしく解説していきます。
1.さつまいもダイエットとは
さつまいもダイエットとは、ご飯やパンなどの主食をさつまいもに置き換えるダイエットのことです。
カロリーや糖質のカットだけなら他の食材でも代用できますが、さつまいもは栄養価が高く、満腹感も得られることから、ダイエットにぴったりの優れた食材なのです。
さつまいもダイエットの発祥は韓国から
さつまいもダイエットの発祥は韓国。韓国で「コグマダイエット」と呼ばれており、2017年に若い女性を中心にブームが起こったのです。
韓国ではアイドルやコメンテーターもさつまいもダイエットに成功したため、注目を集めました。
2.さつまいもに含まれる栄養とダイエット効果
2-1.水溶性食物繊維によって腹持ちがいい
食物繊維は水に溶ける「水溶性食物繊維」と、水に溶けない「不溶性食物繊維」の2種類。
さつまいもにはどちらの食物繊維も含まれています。
水溶性食物繊維は水を吸収して膨張するため、胃に長くとどまりゆっくりと消化されていくので腹持ちがよく、ダイエットに適しているといわれています。
2-2.不溶性食物繊維によるお通じの改善
さつまいもに含まれる不溶性食物繊維やヤラピンは、お通じの改善にも役立ちます。不溶性食物繊維は便のかさを増してくれ、腸の動きを活発にさせるため、便秘の解消が期待できるのです。
便秘が続くと腸内の悪玉菌が増加してしまうため、むくみや血行不良を起こし、どんなダイエットをしても効果が充分に得られない可能性もあるので、お通じの改善はとても大切なことです。
2-3.カリウムによるむくみの解消
さつまいもに含まれるカリウムは、過剰なナトリウム(塩分)の排出を促す効果が期待できます。
さつまいもの他にも、ほうれん草やかぼちゃなどの野菜、メロンやバナナなどの果物、豆類などにも多く含まれている栄養素です。
2-4.ビタミンCやビタミンEによる老化対策
さつまいもに含まれるビタミンCやビタミンEは、皮膚や粘膜の健康維持に欠かせません。
ビタミンCは熱に弱いといわれていますが、さつまいもに含まれるビタミンCは熱にも強い特性があるといわれているので、加熱調理しても多くのビタミンCを摂取することができるのです。
ビタミンEは細胞膜の酸化による老化や血液中のLDLコレステロールの酸化によって起こる動脈硬化などを防止するといわれています。
細くなっても栄養が足りず肌がボロボロになるのは避けたいですよね。きれいに痩せるために欠かせないビタミンCやビタミンEが含まれているさつまいもは、ダイエットに効果的な食材です。
3.さつまいもと他の主食類のカロリーと糖質(100gあたり)
さつまいもが痩せるといわれている理由は、他の主食類とくらべて、カロリーや糖質が低いからです。
同じ量のご飯・パン・パスタとカロリー・糖質の量を比較してみましょう。
カロリー
糖質
さつまいも
134cal
30.9g
ご飯
168cal
36.8g
パン
260cal
44.3g
パスタ
150cal
31.3g
さつまいもがカロリーも糖質も一番少ないことがわかりますね。
また、さつまいもは低GI食品であることもダイエットに向いているといわれる理由の一つ。糖の吸収が穏やかなため、食後の急な血糖値の上昇を防ぎます。
GI値が高いと、食後に血糖値が一気に上がり、身体に脂肪がつきやすくなるといわれています。
4.さつまいもダイエットのやり方
さつまいもがダイエットにぴったりな食材であることはわかりましたが、さつまいもだけを食べればいい、さつまいもさえ摂取していれば何をしても痩せるというわけではありません。
よりさつまいもダイエットを効果的に行うにはどのようにしたらいいのでしょうか。さつまいもダイエットの正しいやり方をご紹介します。
4-1.3食のうち、1食の主食をさつまいもに置き換える
さつまいもダイエットをするときは、朝・昼・晩の3食のうち、1食だけ主食をさつまいもに置き換えてみましょう。量は1/2本(150g)ほどが目安です。
おすすめは、エネルギーとして消費されやすい朝か昼。夕食の場合、消費しきれなかった糖質が体に蓄積されてしまう可能性があるからです。
夜遅くに夕食を取ることが多い場合は、朝か昼に置き換えしてみるといいでしょう。
4-2.さつまいもは皮ごと食べる
ダイエット目的でさつまいもを食べるのであれば、皮ごと食べましょう。
さつまいもの皮は、ダイエットにもうれしい栄養がたっぷり。整腸作用があるヤラピンは皮の近くに、老化対策に役立つアントシアニンは皮に豊富に含まれています。
4-3.バランスの良い食事を摂る
さつまいも単品で食事を済ませてしまうと、栄養バランスが乱れてしまいます。バランスの良い食事を摂るように心がけましょう。
栄養が偏るといわれても、さつまいもをごはんの代わりに食べようとすると、合うおかずが少ないと悩んでしまいますよね。
そんなときは、さつまいもを味噌汁などの汁物に入れたり、炒め物やサラダにしたりするといいですよ。
4-4.さつまいもを冷やして食べる
さつまいもを冷やすと、でんぷんの一部が腸内環境を整えてくれる「レジスタントスターチ」に変化します。
レジスタントスターチは小腸で消化されず大腸まで届き、食後の血糖値の上昇も穏やかにしてくれます。
冷凍したやきいもは、アイス感覚で楽しめるので、どうしても間食がしたくなってしまったというときにもおすすめです。
5.さつまいもダイエットは1週間で効果はでる?
結論からいうと、さつまいもダイエットを1週間ですぐに効果が出るとはいえません。
さつまいもは食べ過ぎに注意しなくてはいけません。目安は一食あたり150g。
毎食さつまいもはさすがに続かないので、1日1回とします。ごはん150gをさつまいも150gに置き代えた場合、1日で約60kcalカットできます。
1週間で420 kcalのため、減量できたという実感はないものの、塵も積もれば山となるので続けていく価値はあるといえます。
6.さつまいもダイエットの基本レシピ
6-1.蒸し芋
電子レンジの場合
さつまいもを洗ってラップで包む。
600Wで5分加熱する。
串が通るよう柔らかさになったら完成。
蒸し器の場合
さつまいもを洗って蒸し器に並べる。
蒸し器に水を半分くらい入れてふたをする。
湯気が出てきたら火を中火にして30分煮る。
串が通るよう柔らかさになったら完成。
6-2.やきいも
さつまいもを洗って、アルミホイルで包む。
150~160℃のオーブンで70~90分焼く。
途中何度かひっくり返す。
串が通るよう柔らかさになったら完成
プラスワン 冷凍後、解凍して食べるとレジスタントスターチも増えて効果的!!
<さつまいもをレンジを美味しく調理する方法はこちら>
https://oimobicho.jp/basic/yakiimo-microwave/
<さつまいもをオーブンを美味しく調理する方法はこちら>
https://oimobicho.jp/basic/yakiimo-oven/
<さつまいもをトースターを美味しく調理する方法はこちら>
https://oimobicho.jp/recipe-column/recipe-toaster/
7.さつまいもダイエットにおすすめのアレンジレシピ
7-1.しっとりさつまいものヨーグルトサラダ
材料
○さつまいも・・・200g
○きゅうり・・・50g
○くるみ (刻み)・・・大さじ1
★ヨーグルト無糖・・・大さじ2
★マヨネーズ・・・大さじ1
○塩・・・ 少々
○黒こしょう・・・ 少々
しっとりさつまいものヨーグルトサラダの作り方
①さつまいもを1cm角切りにし、水に10分さらして水気を切る。
②きゅうりを1cm角切りにし、塩を軽く振り5分おいて水気を絞る。
③①のさつまいもを耐熱容器にいれ軽くラップをかけて、電子レンジ500Wで4~6分加熱する。
④★ヨーグルトとマヨネーズを合わせる。
⑤③に②のきゅうり、★を加えて和え、塩・黒コショウで味を調える。
⑥器に盛り付けて、粗く刻んだくるみを上からふりかけて出来上がり!
7-2.ホクホクさつまいもの具沢山な豚汁
材料(2人前)
○さつまいも ・・・1/2本
〇豚肉・・・150g
〇にんじん・・・1/4本
〇ごぼう・・・1/4本
〇こんにゃく・・・1/2袋
○ごま油・・・大さじ1
○塩コショウ・・・少々
〇和風顆粒だし・・・1袋
〇水・・・500ml
★酒・・・大さじ2
★みりん・・・大さじ1
★しょうゆ・・・小さじ1
○みそ・・・大さじ2
○刻みネギ・・・お好みで
○一味唐辛子(または粉山椒)・・・お好みで
ホクホクさつまいもの具沢山な豚汁の作り方
①さつまいもは水でよく洗い、皮ごと約1.5cm幅の輪切りにし、水に10分ほどさらしておく。
にんじんは水で洗ってから皮をむいて、いちょう切りにする。
ごぼうは、タワシで水洗いをしたから斜め切りをする。
②こんにゃくは塩もみ(塩は規定材料外)してから、食べやすい大きさに切っておく。
③①で下処理したさつまいもと人参とごぼうを耐熱皿に入れてラップをして電子レンジで600w5分加熱する。
④鍋にごま油を入れ中火で豚肉を炒め塩コショウをしておく。
⑤豚肉の色が変わったら③と②と★を加えて中火で4~5分煮る。
⑥野菜が柔らかくなったら弱火にしてみそを溶き入れひと煮立ちすれば出来上がり!
⑦お好みで刻みネギと一味唐辛子、又は粉山椒を加えれば出来上がり!
7-3.さつまいもと具だくさん野菜の豆乳スープ
材料(2人前)
★さつまいも・・・1/2本
★ブロッコリー・・・1/4株
☆人参・・・1/2本
☆しめじ・・・1/4パック
☆鶏もも肉・・・100g
○水・・・300cc
○コンソメ・・・大さじ2
○しょうゆ・・・小さじ1
○豆乳・・・200cc
○バター・・・10g
○塩コショウ・・・適量
さつまいもと具だくさん野菜の豆乳スープの作り方
①さつまいもはよく洗い、皮ごと輪切りにして、水につけておく。人参と鶏もも肉は一口大に切り、しめじとブロッコリーは小房に分ける。
②鍋を熱してバターを入れ、①で下処理した☆の具材を炒める。肉の色が変わったら、水を加える。
③沸騰したら、アクを取り除く。
④①で下処理した★の具材を入れひと煮立ちさせる。
⑤食べる前に豆乳と醤油を加え塩コショウで味を調えて出来上がり!
(注意:沸騰させると豆乳が分離するので、沸騰直前で火を止めましょう。)
8.さつまいもダイエットの典型的な失敗例3選
さつまいもダイエットを始めても、なかなか効果が出ないことも。そんなときは効果がないと諦めてしまう前に、確認してほしいことがあります。
さつまいもダイエットの典型的な失敗例を見ていきましょう。さつまいもダイエットの失敗についてはこちらの記事でもくわしく紹介しているので、参考にしてみてください。
さつまいもダイエットに失敗!?参考にしたい失敗理由3選
8-1.さつまいもを食べ過ぎる
さつまいもだからといって、安心して過剰に摂取していませんか?先ほどもご紹介のとおり、目安は1/2本(150g)です。
栄養が取れるからといって、主食の炭水化物を減らすことなく、いつもの食事にさつまいもをプラスするのも過剰摂取になるため気をつけましょう。
8-2.脂質や糖質を多く含むアレンジをする
さつまいもは、ご飯のおかずにも、スイーツにもなる、レシピが豊富な食材です。
いつも同じ食べ方では飽きるので、工夫するのはいいことですが、脂質や糖質を多く含むアレンジはダイエットには不向き。
揚げ物にしたり、砂糖やバターを多く使ったりするレシピは避けましょう。
8-3.一緒に食べているおかずが高カロリー
さつまいもを食べているからといって、何を食べてもいいわけではないため、高カロリーなおかずと一緒に食べるのはNG。
さつまいも以外の食材も脂質や糖質が多いものは避けて、バランスの良い食事を心がけましょう。
まとめ
さつまいもはご飯などの主食にくらべ、低カロリーで糖質も低い食材なため、ダイエットに効果的といえます。
即効性はないものの、お通じの改善も期待でき、腹持ちもいいので、無理なくダイエットできる食材です。
より効果的に行うためにも、皮ごと使用したり、調理方法によって高カロリーにならないように気をつけたりする必要はありますが、レシピが豊富なので飽きないのもさつまいもの魅力の一つ。
また、毎日さつまいもを蒸したり焼いたりするのが正直めんどう…という方にピッタリなものがあります!
それが、【らぽっぽファームオンラインショップ】の美腸やきいもです!
詳しくはこちら。
↓↓↓↓↓↓
とっても甘い「紅はるか」を皮ごと使用し、じっくり焼き上げた冷凍の焼き芋です。
さつまいもダイエットのポイントとなる、
・皮ごと調理して食べる
・やきいもにして冷やして食べると効果的
を満たしていて、手軽に手に入るのも魅力的!
1袋150gの小分けパックになっているので、食べ過ぎの心配もいりません。
ただし、焼き芋にすると水分が抜けるため、同じ150gでも「生のさつまいも」よりも「焼き芋」の方がカロリーが高くなってしまいます。
置き換えダイエットのときは、美腸やきいもを1袋全部食べるのではなく、少し残すのがポイントです!
美味しいさつまいもの選び方とは?さつまいもの選び方のポイントを解説!
スーパーでさつまいもを選ぶときには、やっぱりおいしいさつまいもを選びたいですよね。しかし、野菜コーナーに置いてあるさつまいもは形も大きさも様々。
おいしいさつまいもとはどのような特徴があるのでしょうか。この記事ではおいしいさつまいもの選び方のポイントやさつまいもの保存方法を解説します。
1.美味しいさつまいもを正しく選ぶ方法
1-1.ふっくらとした丸みのある形
身の詰まった美味しいさつまいもは、レモンやラグビーボールのような、中心が太く端が細い形をしています。
ふっくらとした形で、丸くなりすぎていないものを選びましょう。
中央が膨らんでいれば膨らんでいるほど良いのかというと、そういうことでもありません。中央が膨らみすぎているものは、成長の段階で深い位置で身を付けてしまい、地中が固いせいで実がキレイに伸びなかった可能性があり、その場合は十分な糖度が蓄えられていない可能性があります。
丸すぎず、細すぎないものを選ぶ
同じ株で育ったさつまいもでも、地上に近いところのさつまいもは、土が柔らかいため縦に伸びますが、地中深くで育ったさつまいもは縦には大きくなれない分、横に大きくなる傾向があります。
地中の深いところでは、水分や栄養が十分にあるため、身に栄養を蓄えなくても良いのですが、地表から浅いところでは、水分がどんどん無くなる太陽の近くで生き抜くため、身に栄養を蓄えることで甘さが強くなると言われています。
1-2.身が詰まって重たいもの
さつまいもは、持った時にずっしりと重みを感じるものが良いです。軽いさつまいもは繊維質が多くなってしまい、ボソボソとした食感になっている場合があります。
1-3.表面に凹凸やひげ根の少ないものを選ぶ
さつまいもの表面には窪みがありますが、この窪みが浅い方が繊維質が少なく、甘く食べやすいさつまいもです。
逆に窪みが深かったりひげ根の多いさつまいもは、身が痩せてしまっていて、味が落ちている可能性があります。
1-4.皮がキレイで、艶があるものが良い
皮が艶っぽく手触りの良いさつまいもは、身のキメも細かく食感が柔らかい傾向があるので、凹凸が少なく手触りの良いものがお勧めです。ですが、皮の一部が変色していたり、傷のあるものは中が傷んでいる場合があるので避けましょう。
1-5.蜜が出た後がないか
さつまいもは、カットされた両端に黒っぽい液の跡がついていることがあります。これは、さつまいもの甘い蜜が溢れてついたものなので、この跡があるさつまいもは、糖度の高い甘いさつまいもの可能性が高いです。
2.甘くて美味しいオススメのさつまいもの品種
2-1.安納芋
安納芋は、さつまいもの出荷量日本1を誇る鹿児島県の種子島で作られるさつまいもです。皮が赤い「安納紅」と、そこから派生した皮の色が白い「安納こがね」などの種類があり、種子島でしか栽培することができない希少なさつまいもです。
身の水分量が多く焼き芋にするととろけるような食感になるのが特徴です。
2-2.シルクスイート
シルクスイートは、レモンのような中央がふっくらとしていて両端が細い形をしていて、紅色のやや小ぶりで、中の身は白〜クリーム色な見た目をしているさつまいもです。
2012年に開発された新しい品種ですが、テレビでも取り上げられるほど人気な品種です。
2-3.なると金時
中身が黄金色をしている芋を金時(きんとき)芋と呼んでいたことから、「なると金時」と名づけられました。
見た目も鮮やかな黄金色のなると金時は、栗のようにホクホクとした食感と、糖度が高めなのが特徴な品種です。
定番の焼き芋はもちろん、菓子の材料などにもよく使われておりスウィートポテトなどにもおすすめです。
2-4.紅はるか
紅はるかは蒸し芋にしたときの糖度が高く、食べてみると強い甘さにもかかわらず後口はすっきりした感じの上品な甘さを感じることができます。
加熱するとしっとりとした食感に成り、焼いた時の甘さはあの安納芋とも比較されるほどです。
3.さつまいもを保存する際の注意点
さつまいもを保存する際は、土を水で洗い落としてしまうのは厳禁です。
水で洗い流してしまうと傷がついて部分から腐りやすくなってしまうため、さつまいもを保存する際は土は洗い流さないようにしましょう。
さつまいもの正しい保存方法についてはこちらの記事で詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。
https://oimobicho.jp/basic/expiration-date/
まとめ
おいしいさつまいもの選び方について解説しました。形や丸み、皮がきれいで艶があるかどうかなどを確認しましょう。
おいしいさつまいもを購入して保存する際は、水洗いなどをしないように気をつけてくださいね。