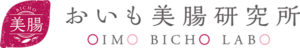保存していたさつまいもにカビが生えてしまい、食べてもよいのか悩んだことはありませんか?
カビが生えた部分だけ取り除くことで食べられるのであれば、捨ててしまうのはもったいないですよね。
この記事では、さつまいもにカビが生えたときの見分け方やカビを生えにくくする保存方法などを解説します。
目次
1.さつまいもにできるカビは取り除けば食べられる?

さつまいもを食べるとき、口に含んでも大丈夫なカビもありますが、体内摂取することはおすすめできません。
カビを知らずにいつの間にか食べてしまった経験のある方も、なかにはいるのではないでしょうか。
基本的には、カビを取り除いたさつまいもなら大丈夫です。
詳しく深堀りしてみていきましょう。
1-1.カビの種類によっては取り除けば食べられる
さつまいもにカビが生えているのを見かけたらもう食べられないと思うかもしれませんが、じつはカビの種類によってはカビとその周辺部分を取り除けば食べられるようになります。
カビを放置してしまうと実が腐ってしまうため、気づいたらすぐに取り除きましょう。
1-2.さつまいもにできるカビの種類と見分け方
さつまいもにできるカビの種類は、下記の4つです。
- 白カビ
- 青カビ
- 緑カビ
- 黒カビ
カビたさつまいもの臭いだけでは違いがわかりにくく、かといってブヨブヨした状態では見た目も判断つきません。
そもそも、洗った後のさつまいもは早ければ1週間もしないうちにカビやすいです。
ここでは、さつまいもに生えるカビの特徴と見分け方をまとめました。
白カビ(取り除けば食べられる)
さつまいもの皮に、白い綿のようなものが付着している場合は白カビです。
白カビが生えていた場合は、よく洗ったあとにカビが生えた部分とその周辺を取り除き、加熱調理をすれば食べられます。
切ったときに黒ずんでいるときは、傷んでいる可能性が高いため、黒ずみも一緒に取り除いてください。
青カビ(取り除けば食べられる)
さつまいもの両端が、濃い青のような色になっている場合は青カビです。
白カビと同じく、カビが生えた部分とその周辺を取り除き、加熱調理をすることで食べることができます。
金属製の調理器具に反応して、本来黄色であるさつまいもの実が青黒くなることがあります。
これはカビではなく、さつまいものクロロゲン酸と調理器具の鉄が反応し、タンニン鉄が作られただけ。有害物質ではないため、食べてもOKです。
緑カビ(取り除けば食べられる)
さつまいもの緑色は、クロロゲン酸による変色です。
しかし、アスペルギルスやペニシリウムを起因とする緑カビがさつまいもに付着していることもあるため注意しなければなりません。
緑カビは、クロロゲン酸による変色とは一見して判別しにくいためです。
強いていえば、さつまいもの表面にうっすら粉っぽく乗った感じのものが緑カビですが、クロロゲン酸による緑色の変色は浸み込んだ見た目をしています。
緑カビのアスペルギルスやペニシリウムは、くしゃみや鼻水などのアレルギー症状がみられる場合があり、食べないよう注意しましょう。
ちなみに、緑カビは青カビとも見た目が似ており、色の判別もしにくいです。
黒カビ(毒性が強く、内部にも繁殖して食べられない)
通気性が悪い状態で保存しているさつまいもは、湿気が原因で黒カビが発生することもあります。
黒カビが生えたさつまいもは毒性が強く、内部にも繁殖しているケースが多いため、食べない方がいいでしょう。
斑点状に黒いものがついている、白カビ同様に綿のようなものが一緒に付着している場合は黒カビです。
蜜のような黒いものが、かさぶたのように固まっているときは、カビではなくヤラピンの可能性も。ヤラピンについては、この記事後半でも少し触れます。
ヤラピンはさつまいもを代表する栄養素なので、食べても問題はありません。
2.さつまいもにカビがなくても腐って食べられない場合がある!

カビが生えていなくても、保存状態が悪いとさつまいもが腐っていることがあります。
悪臭がする、水分が抜けて皮がシワシワで実がスポンジのようになっている、触ったときにブヨブヨと柔らかくなっているという場合は、腐っている可能性が高いので注意しましょう。
また、見た目や臭い(におい)に問題はなくても、食べたときにさつまいもとは思えない酸味や苦味を感じるときは腐っているため、処分してください。
3.さつまいものカビの発生を防ぐには?
3-1.さつまいもの保存場所
さつまいもにカビが生えない、保存に適した場所はキッチンや玄関、床下収納や廊下といった割と普通の場所です。
室温の変化があまりなく、風通しの良い、日光があまり当たらない場所。これらの条件を満たせる場所であれば、上記の場所以外で保存しても問題はありません。
3-2.さつまいもの保存方法
さつまいもの最適な保存温度は、14℃〜16℃です。
保存温度を10℃以下にしてしまうと、低温障害になり鮮度が低下する可能性が高まります。
そのため、冬場での保存は段ボール箱に丸めた新聞紙や、おが屑などをさつまいもと一緒に入れておくことで、温度が下がることなく保温することができます。
ただし、閉め切った状態にしてしまうと湿気がこもって傷みやすくなるため、段ボール箱や発泡スチロールに入れて保存する場合は、蓋を外したり穴を開けたりするなどして、さつまいもが呼吸できる環境を作ってあげましょう。
さつまいもの保存方法については、こちらの記事でも詳しく解説しているので参考にしてみてください。
4.カビたさつまいもを食べてしまったらどうなる?

さつまいものカビは、食べてしまうとマイコトキシンなどの毒素から食中毒を引き起こしてしまう場合もあり、嘔吐や吐き気、下痢などの症状がみられるようになります。
ちなみに、さつまいもの皮部分にみられる黒い部分もカビと間違われやすいため補足します。
ヤラピンという成分で、黒い蜜のようにもみてとれますが、カビではないので食べてしまっても大丈夫です。
それでは、カビたさつまいもを食べたらどうなるのか「食中毒」「過敏性腸症候群」という観点で解説します。
4-1.食中毒
カビたさつまいもを口にしてしまうと、カビの毒素で食中毒になってしまう恐れもあります。
前述にて紹介したカビの種類ごとに、毒素の特性を下表でまとめました。
| カビの種類 | 毒素の種類 |
| 白カビ | マイコトキシン |
| 青カビ | プベルル酸、マイコトキシン |
| 緑カビ | アスペルギルス、ペニシリウム |
白カビは、断面や表面にふわふわして白い線が出ておりマイコトキシンを産生します。
マイコトキシンは真菌毒素で、1週間以上放置したさつまいもでよくみられるプリズム色のカビです。
掃除が行き届いていない不衛生な環境でさつまいもを保存していると、カビが繁殖しマイコトキシンで汚染されてしまいます。
雨の日など湿度が70%を超える環境下でも、さつまいもはカビやすいです。
また、青カビでみられるプベルル酸は黄色の粉末状で、食中毒の原因となるため口にしないように注意しなければなりません。
コウジカビとも呼ばれるアスペルギルスやペニシリウムは、緑カビでみられますが、土壌や堆肥の残留物から汚染されます。
さつまいものカビ毒素による食中毒で嘔吐や吐き気、下痢、発熱、腹痛、頭痛などの症状に悩まされるでしょう。
4-2.過敏性腸症候群
カビたさつまいもを食べたら、過敏性腸症候群が悪化しやすくなります。
過敏性腸症候群自体、植物性の食物繊維を過剰摂取することで腹痛や下痢などを引き起こすのですが、ここではさつまいものカビも影響するので解説しています。
そもそも、食物繊維を含むさつまいもを食べ過ぎるのも、過敏性腸症候群の要因となる場合があるためよくありません。
また、さつまいもを食べたときに含まれるマイコトキシンなどのカビ毒素で、腹部膨満感や腹痛、下痢の症状が悪化します。
さつまいもも食物繊維を含むことから、FODMAP(フォドマップ)と呼ばれる小腸で消化されにくく、大腸では発酵しやすい糖質としても捉えられています。
つまり、さつまいもの食物繊維は体内で消化されにくく、カビが侵入した際に過敏性腸症候群を悪化させてしまうということです。
ちなみに、FODMAPは発酵性オリゴ糖、二糖類、単糖類、ポリオールの頭文字です。
腸に異常がみられないのに突然、カビに気付かずさつまいもを食べただけで、慢性的な腹痛や下痢などの症状に悩まされてしまうことがあるため注意しましょう。
まとめ
さつまいもは長期保存できる食材ですが、保存方法などによりカビが生えることがあります。
白カビと青カビ、緑カビは取り除けば食べられますが、黒カビは危険なため処分した方がよいでしょう。
また、カビが生えていない場合でも、悪臭がするなどいつものさつまいもと様子が違うときは腐っている可能性もあるので注意してください。
さつまいものカビを防ぐには、直射日光を避け、風通しのよい場所で保存するのがベスト。冷蔵庫で保存する場合は、低温障害にも気をつけましょう。
長持ちするさつまいもですが、購入後はなるべく早めに食べる方が美味しいです。
くれぐれもカビが生えたまま放置はしないでください。
さつまいも、1から自分で育てるのは大変そうだけど、芋掘りは体験してみたいなと思ったことはありませんか?そんな方には 世界一のおいも掘りの聖地と言われている【らぽっぽ なめがたファーマーズヴィレッジ】がおすすめです。
詳しくはこちら。
↓↓↓↓↓↓
ぜひフォローをお願いします。