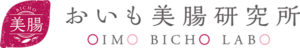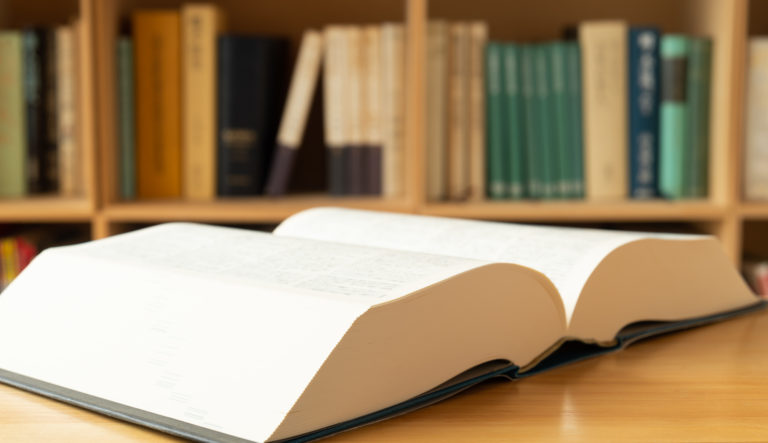
これからさつまいもの季節になってきました。栄養がたっぷりで、今や女性が大好きなこの食材がどうして「さつまいも」とよばれるようになったのかご存知でしょうか?
日本にくるきっかけになったことも踏まえ見ていき、知識を深めていきましょう!
1.さつまいもの由来

さつまいもの原産地は南米といわれています。
長年かけて世界中に広まったとされていますが、南米からフィリピンに伝わり、1500年代後半にフィリピンから中国に伝わりました。
フィリピンで栽培されたさつまいもの持つ栄養が穀物に匹敵する食材であることに驚き、中国人の陳振竜が、甘藷のつるを船の舳綱に巻いて、ひそかに持ち出したといわれています。
持ち出した甘藷を、陳は金学曹という地方役人をしている人に献上し、飢えに苦しむ人びとを救うために甘藷の栽培を国中に広めていきました。
そして1600年頃日本に中国からさつまいもがやってきました。
さつまいもを漢字で「薩摩芋」と書きます。
さつまいもという名の由来は、、1600年ごろ、琉球(今の沖縄県)から薩摩(今の鹿児島県)に伝わったものなのです。
2.他にもある!さつまいもの呼び方
2-1.甘藷
薩摩芋の中国名で「甘藷(カンショ)」と呼ばれることも多いです。「甘い芋」を意味しています。
薩摩芋の次に聞き覚えのある名称ですよね。
2-2.唐芋
中国(唐の国)から伝わってきた芋というのが由来で「唐芋(カライモ、トウイモ)」とも呼ばれています。
2-3.琉球芋
琉球(今の沖縄県)から伝わった芋という意味で「琉球芋」とも呼ばれていました。国や地域の名前が由来になることが多いようです。
2-4.十三里
江戸時代に入り、徐々に栽培地域が広まってくると、甘くて美味しいさつまいもを、栗より美味しい芋として「十三里」と呼んでいました。
焼き芋は江戸にも伝わり、焼き芋屋さんが、「十三里」と名付けたところ 「栗(九里)より(四里)うまい十三里」という洒落が江戸っ子に評判を生み、それから「さつまいも=十三里」となったようです。
さつまいもを「十三里」と呼ぶことから、1987年に埼玉県川越市の「川越いも友の会」が、旬にあたる10月13日を「さつまいもの日」としています。
まとめ
さつまいもにもいろいろな漢字、呼び方があったんです。
輸入先の地名で呼ばれることが多かったようですね。
昔からさつまいもは必要とされており、色んな国や人々に愛されていたことがわかりました!
ぜひフォローをお願いします。